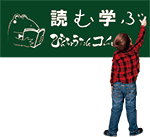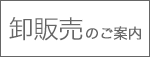プレマシャンティからの贈り物「辺見さんの手作りどら焼き」
ギフトにも最適です。プレマシャンティオリジナル商品紹介カードを添えてお届けします。

プレマシャンティは、繋がりのなかで生まれます。
それは人であったり、自然であったり、商品であったりします。
ご紹介頂いたご縁を辿って各地を旅するうちに、その土地だからこその出会いもあります。
その土地でしか、その時期にしか出会えない味。
皆さんにご紹介したいけれど、生ものであったり、作る量が限られていたりと、私たちがお預かりするには難しい商品も決して少なくありません。
また作り手を身近に感じて初めて、より深い味わいが生まれる商品もあります。
プレマシャンティの開発チームが、各地を巡り、作り手の目を見て、言葉を交わして惚れ込んだ数々を、桜のカードを添えてお届けします。
和菓子職人 辺見さんに会いにいきました
島根県安来の瀬尻製パンには、日本でたったひとり残った「ちどり羹」の技術を引き継ぐ職人がいます。辺見登さん。
御年80歳。15歳で和菓子の道に進んで以来、この道一筋の和菓子職人です。
隠岐の島に渡り、和菓子と洋菓子、パン作りに取り組んでいた頃には、当時皇太子であられた現平成天皇ご夫婦が島をご訪問された際に、朝食用のパンを献上されました。それだけではありません。辺見さんは再び、「ちどり羹」の作り手として、陛下に献上する機会を得ます。安来の銘品「ちどり羹」は、白小豆の白あんを寄せ、小豆をちらして固めた和菓子です。
寒天を使い固める羊羹とは似て異なり、一子口伝で製法を引き継ぐ幻の菓子です。裏千家などの茶会では欠かせないにも関わらず、幻の菓子と呼ばれる理由は、もう今では作られていないから。
復活を望む声が多い中、たったひとり製法を知る辺見さんは、「ちどり羹は『眞月堂(しんげつどう)』のお菓子。だから『眞月堂』がなくなった今は、ちどり羹はちどり羹じゃあないね」と、決して首を縦には振りません。
そんな辺見さんが、瀬尻製パンでつくっているのは「どら焼き」です。
辺見さんがコテを差し込むと、ほわっと甘い香りが揺らぎます。


熱く熱した銅板の上にたらりと流す生地が、ゆっくりと10センチくらいの大きさの円に広がります。広がりきるのを待たず、次、次と、縦に4個。その隣にまた4個。途切れることなくリズミカルに、縦4個の列が6列、丸い円盤型の生地がアツアツの銅板いっぱいに、ただ音もなく並びます。面白いくらいに同じ大きさの円盤が、合計24個揃ったら、ここからは、しばらく火の仕事。
ガスバーナーの直火を受ける銅板が、食欲をそそるきつね色に生地を焼き上げます。片面2分。
裏返すタイミングは、生地が教えてくれる。
という辺見さん。
クセのように必ずタイマーのボタンを押すのに、小さなコテを手に生地を返し始めるのは、いつも電子音が時間を知らせるかなり前です。
表面にふつふつとね、気泡が出てくる。それが合図。
辺見さんがコテを差し込むと、ほわっと甘い香りが揺らぎます。
薄く黄味を帯びた生地の裏側は、こんがりきつね色。まるでオセロのように、次々ときつね色があらわれて、銅板一面を覆ったかと思ったら、そのままの手で今度は火からおろしていきます。
さっきまでなま生地色だった裏面は、数十秒できつね色に変わっていました。
ホットケーキを焼くのと同じ要領ですか?
と尋ねると、YESでもなくNOでもなく、
焦がさないようにって、火を弱くするとね、生地が固くなる。
ぼさぼさしておいしくないの。
こう、ある程度、強い火で焼かないと。
と教えてくださいました。
焼きあがった生地の厚さは5ミリ。
歯切れがいいのにもっちりねばりがある、
相反する要素が両立した独特の食感です。

最近のどら焼きの生地は厚くて、こう、縦に気泡がはいっているでしょ。
ぷつぷつと、大きな気泡が。
どら焼きの生地なのに、カステラみたいに気泡がたくさん。
膨張剤をいれると、ああなります。
でも食べるとね、生地がパサパサで、あれは違うよね。
焼きあがった生地の厚さは5ミリ。歯切れがいいのにもっちりねばりがある、相反する要素が両立した独特の食感です。
しっとりと焼きあがった生地をそのまま頂くと、甘い香りはもちろんですが、あっさりとした甘みの後を小麦の風味が追いかけます。
「夜店の屋台のベビーカステラを、最上級に品よくした味」と表現すると、辺見さんに苦笑いされましたが、どこか懐かしい、子供の頃の記憶を揺さぶる味と香りなのだろうと感じます。
北海道産の薄力粉、種子島の粗製糖、地元の米粉と卵、九州の蜂蜜、本みりん、重曹。薄力粉にはふすまも混ざっています。
粒あんなのに、さっと溶けて四散するさらりとした食感です。


焼きあがった生地の粗熱を取ったあと、冷めすぎないうちに小豆餡をはさみます。
小豆餡も、もちろん辺見さんの手によるもの。
ゆっくりと炊き上げた小豆に砂糖を加え、しばらく甘さをしみ込ませた後に煮詰める製法は、和菓子屋さんの製餡のやり方だといいます。
適当に豆を柔らかくして、水分を含ませて、それからあくる日にまず炊いて、柔らかんなるまで炊いて、2-3時間かな。
それから砂糖を入れてね。
ほんとはね、一日砂糖にいれて置いとくところもあるけど、うちは大体半日ぐらい、5-6時間、豆とあわして、それから炊きあげるの。
火を入れないで、豆がね、砂糖の糖分を自然に吸い取るまで待ってね、それから火を入れて練り上げるの。
そうするとね、小豆の皮も柔らかんなるの。
最初から砂糖を入れて火を入れるとね、皮が固くなって口の中で残うやん。それはね、あんまり早く火を通しすぎ。
つやつやと光る小豆餡は、山陰好みの濃い甘みでありながら、舌にまとわりつくような、水分で流したくなる甘みではありません。
粒あんなのに、さっと溶けて四散するさらりとした食感です。
「好きなだけはさんで、食べていいよ」
と頂いた焼きたての生地と、トレーいっぱいの小豆餡を目の前にして、至福のひと時。
まずは生地、そして餡だけ。それぞれを味わったのちに、次はどら焼き。
単体では甘みが強いと感じた餡が、生地と一緒になった途端、甘さは控えめ、小麦の風味を引き立てる名わき役に転じたのには、心底驚きました。
味は味覚と嗅覚と視覚によって出来上がるとは、まさにこのことです。

焼きたての小麦のかおりと香ばしさ。
そして、餡の風味。
ふたつが互いに引き立てあって
初めて生まれるどら焼きは、
大好きなひとと分け合って
頂きたい寒い季節だけの贈り物です。



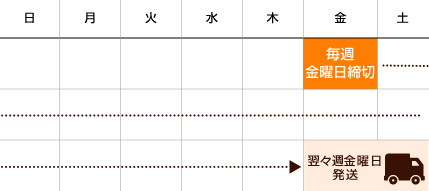





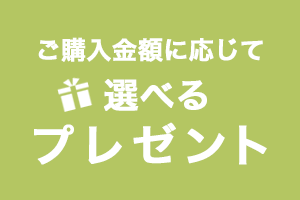
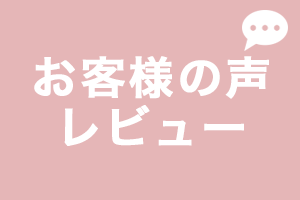
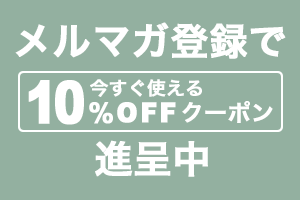
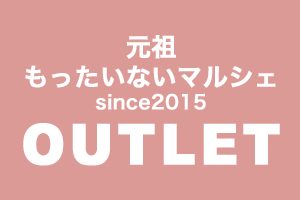
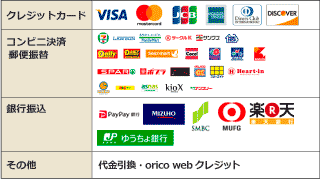











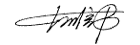










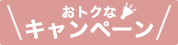




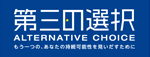




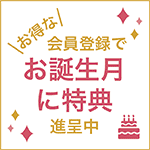
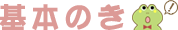
 がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)
がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)