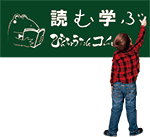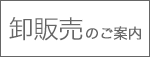日本の夏、京すだれの名匠を見つけました
「京すだれ川﨑」完全レポート
15年ではまだまだ、20年してやっといい葭を見分けられるようになる。
「炭澄スクリーン」は販売終了いたしました。
ご愛顧ありがとうございました。

『京すだれ 川﨑』の親方、川﨑音次さんとともに
| レポート: 写真: 金魚のふん: |
川井悠央 松下由紀 佐々田葉月 |
| ■この道40年、やっと良いもの・悪いものがわかるようになってきた | ||
川﨑親方は15歳でこの道に入った。それから40年、今では京すだれの手編みをする職人の方が少なくなって、日本で4軒ほどしか本当にいいものを作れる人はいなくなったという。独立したのは26歳。 親方「その当時は良いも悪いも何にもわからなかった。それが自分が年いって、最近ちゃうかな、いいもの、悪いものが分かるようになってきたのは」
親方は手に持った葭を、節のところで何気なくポキッ、ポキッと折るようにして曲がりを修整している。これを『節折り』と言う。 親方「これが一番難しいところで、上手・へた、に10年はかかる」 間じかで見ていて初めてその技のすごさが伝わってくる。力を入れすぎたら折れてしまうし、修正の方向を間違えたら、まっすぐな編みやすい材にはならないであろう。知れば知るほど奥が深い。
|
| ■高級葭(よし)について | |||
良材の選定はたいへんだ。昔から上質の葭は琵琶湖の東岸で採れる葭だが、最近は琵琶湖の富栄養化で、葭が太くなり、すだれ用の細い葭は少量しか採れなくなくなった。 そこで親方は、中国天津から毎年1~2トン輸入している。中国産はほとんど安価なすだれに使われるのが通常だが、中には琵琶湖産に劣らない良い品質のものが採れるという。毎年定期的に輸入し、その中からほんの一握りの良質な葭を選びだす。
表に止めてあったバンの中には葭が満載されていた。親方自ら青森まで買い付けに行ってきたというから驚きだ。送ってもらったら送料のほうが高くついてしまうので無理もない。
さらに、その中でも最上品の『さび葭』を見せてもらった。寝かしておくと白く粉がふいてくるため、『さび葭』といわれる。なんともいえない渋さと気品を醸し出す。 これは皮付きのままお茶室に使われる。 そう言われれば、西園寺公望公のお茶室に、『さび葭』が使われていたのを思い出す。 |
|||
| ■これぞ宝庫!?資材置き場を拝見 | |||||||
二階の材料置き場を見せていただいた。 「この部屋にいるのが一番好きなんです」 親方の顔がさらに緩む。材にによっては50年も寝かせたものがある。光が入らないようにし、温度・湿度を管理する。世界中から集めた、最上の、葭、蒲(がま)、萩(はぎ)、竹ひご、これら全部が自分の子供のように感じるのであろう。
|
|||||||
| ■製造過程から見る良品の見分け方 | |||
親方「この機械がなくなったら、すだれ作りはもうできなくなる」
|
|||
■新開発:炭すだれ-巧の技が現代素材に生かされる- |
|||
川﨑さんでは糸にも大変なこだわりがある。糸の途中に中継ぎないのが川﨑さんの製品だ。はじめから使うひもの長さを計算し、途中で糸を継がなくてよいようにする。
|
|||
そしてついにできあがりました!
こちらが「炭澄スクリーン」
炭のパワーでシックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドを吸収
マイナスイオン・遠赤外線効果で快適な室内環境を!!

備長炭すだれ『炭澄スクリーン』のご紹介・ご注文はこちら










 作業場に入らせてもらった。手前から奥まで、すだれを編む機械が並んでいる。どの機械も50年から80年も使われた年季ものだ。
作業場に入らせてもらった。手前から奥まで、すだれを編む機械が並んでいる。どの機械も50年から80年も使われた年季ものだ。

 岡山県はもともとビニールパイプの産地で、材料に一割ほど墨の粉を混ぜ込み開発したのが炭すだれだ。
岡山県はもともとビニールパイプの産地で、材料に一割ほど墨の粉を混ぜ込み開発したのが炭すだれだ。

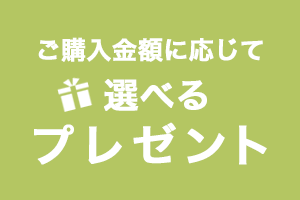
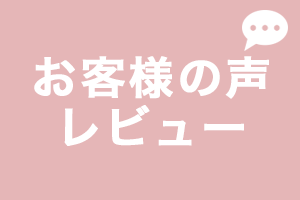
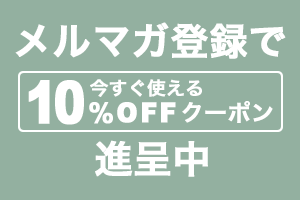
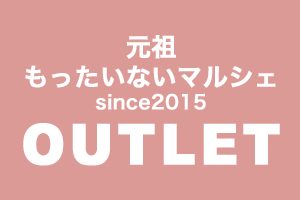
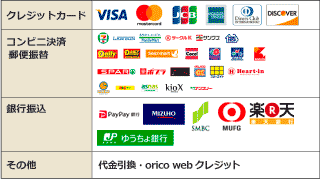











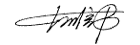










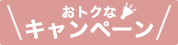




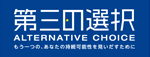



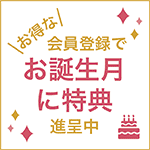
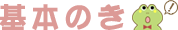
 冷えがちなのですが、マクロビオティックでのおすすめの入浴法は?
冷えがちなのですが、マクロビオティックでのおすすめの入浴法は?