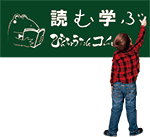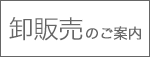腸内環境を整える!腸活特集
健康でいきいきとした毎日を過ごすためには腸内環境を整えることが不可欠です。

その不調、腸からのSOSサインかもしれません。
腸は私たちの健康と深く関わる重要な臓器であり、
いつまでも健康で人生を楽しむためのカギを握っています。
腸を整える「腸活」を始めることで、
病気にかかりにくくなり、心も安定しやすくなって、
健やかさと美しさを保てるようになります。
今すぐ「腸活」を始めて、健康でいきいきとした毎日を送りましょう。
| 腸の重要な役割 | 腸内フローラとは? |
|---|---|
| 腸はただの消化器官ではなく体の健康を支えるさまざまな役割を果たしています。 | 腸の働きのカギを握る腸内細菌。総数100兆個以上!? |
| 腸内フローラを整えるためには? | |
| 腸内フローラは、私たちが健康でいられるか、病気になるかを左右する、きわめて重要な要素です。腸内フローラを整えることこそが心と体の健康維持に直結していると考えられています。 | |
| 腸は全身の臓器と連携して健康を守る存在 | 便でわかる健康チェック |
| 腸は消化だけではなく、体全体の健康や精神状態に大きな影響を与える重要なばある程度の腸内環境器官です。 | 毎日の便を見ればある程度の腸内環境の状態がわかります。 |
腸の重要な役割

消化と栄養の吸収
腸は、食べ物を消化・分解し、体に必要なエネルギーや栄養素を吸収し、残りかすを便として排泄します。特に小腸は、ビタミンやミネラルの吸収において重要な役割を果たしています。
免疫機能
腸は体全体の免疫機能の約70%を担っており、食事や呼吸のときに体内に入ってくるウイルスや細菌を撃退する機能を持っています。腸内環境が整っていると、免疫力が高まり、病気にかかりにくくなります。
代謝とホルモンバランス
腸はホルモンの調整にも関わっており、エネルギーの代謝や体重の管理に影響を及ぼします。腸内環境が乱れると、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まります。
質の良い睡眠
眠気を催すメラトニンというホルモンは、トリプトファンと呼ばれる物質によって生み出されますが、トリプトファンは体内に取り込んだタンパク質を腸内細菌が分解・合成することで作り出されます。腸内環境が整うと、そのトリプトファン生成の効率がよくなり、良い睡眠が取りやすくなるのです。 睡眠の質は、免疫力の向上や肥満防止につながります。
老化予防
老化は年齢を重ねることによる影響だけではなく、細胞や組織の炎症によっても起こります。腸内環境を整えると免疫細胞が良い状態に保たれ、炎症をおさえられるため、老化予防につながる可能性があると言われています。
腸は単に消化器官というだけでなく、体全体の健康を支える重要な存在です。腸内環境を整える「腸活」を行うことで、免疫力アップや精神の安定、生活習慣病の予防といった多くのメリットが期待できます。
腸内フローラとは

腸の働きのカギを握るのが、腸にいる多くの腸内細菌です。およそ500~1000種類で総数は100兆個以上といわれています。
これらは勢力争いをしながら数のバランスを取り、一種の生態系を形成しています。これが腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)で、腸壁に腸内細菌がお花畑のようにびっしりと分布していることから、「腸内フローラ」とも呼ばれています。
理想的な腸内環境は、腸内細菌の種類が多いこと、善玉菌が多いこと、バランスがよく安定していること、です。
腸内細菌は大きく分けて次のように分類されます。
| 種類 | 理想のバランス | はたらき | 菌の名前 |
|---|---|---|---|
善玉菌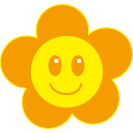
|
2 | 乳酸や酢酸、酪酸を産生し、悪玉菌の増殖を抑える。 | ビフィズス菌乳酸菌(アシドフィルス菌) フェカリス菌 等 |
悪玉菌 |
1 | 悪臭のもととなるガスや、大腸がんの原因ともなる腐敗物質を生成する。 | ウェルシュ菌 大腸菌(毒性株) ブドウ球菌 等 |
日和見菌 |
7 | 人の体の状態によって、有用にも有害にも働くことがある。 | 連鎖球菌 大腸菌(無毒株)等 |
腸内フローラ(腸内細菌叢)の多様性が崩れると…
腸内フローラの乱れを引き起こす原因として挙げられるのが
・塩分や砂糖の摂りすぎ
・抗生剤などの薬の多用
・加齢
・食物繊維の不足
・ストレス
などです。
食物繊維は近年日本人に不足していると指摘されており、積極的に摂るべき栄養素です。
腸内細菌叢のバランスが崩れてしまうと、腸内腐敗が進行し、健康に有害な物質(アンモニア、フェノールなど)が増加します。そうなると、便秘や下痢、肌荒れ、アレルギー、慢性疲労、生活習慣病、脳機能障害などを引き起こして生活に支障を来すようになります。
さらに免疫力の低下を招き、風邪をひきやすくなったり、肥満、アレルギー、炎症性腸疾患、認知症や発がん物質の生成にも関与していることが最近の研究によってわかってきました。
腸内フローラを整えるためには

以上のように、腸内フローラの乱れを放置していると、数多くの不調や病気を引き起こすことがわかっています。
病気を予防するためには、腸内フローラを整えることがとても重要なのです。
具体的には、次のようなことに気を付けることをおすすめします。
プロバイオティクスとプレバイオティクスを摂ること
「プロバイオティクス」
プロバイオティクスとは、腸内フローラのバランスを整え体に有益にはたらく微生物のことを言います。具体的にはビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌などの善玉菌のことを差します。
味噌や納豆、酢、甘酒などの発酵食品もプロバイオティクスです。
大腸内に定着しづらいため、継続して摂ることが大切です。
「プレバイオティクス」
前述のプロバイオティクスに対して、善玉菌のエサになる難消化性成分、食物繊維やオリゴ糖などのことを言います。既に大腸にすんでいる善玉菌を増やす目的があります。
これら「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」を同時に摂ることを「シンバイオティクス」と言います。
善玉菌を摂ることと、そのエサも同時に摂ることで、腸内フローラを整える効果が期待できると言われています。
食物繊維のおはなし

かつて食物繊維は、人間の栄養にはならないものと捉えられていました。
ところが、便のカサや水分を増やして排便を促す働きや、腸内の毒素を体外に排出する働きがあることがわかり、「第六の栄養素」として注目を浴びるようになりました。
近年になり、さらに食物繊維が善玉菌のエサになっていることや、腸内フローラの乱れを正す働きがあることがわかり、食物繊維こそ腸内フローラを整えるための最も重要な栄養素として注目されています。
ところが、先に述べたように現代の日本人は食物繊維の摂取量が足りていないと言われています。
食物繊維の種類と特徴
食物繊維には水溶性と不溶性の二種類がありますが、一般的に食品から摂りにくいのが水溶性食物繊維です。そのため、水溶性食物繊維をいかにして摂取するか、が課題となっています。
不溶性食物繊維はイモ類、豆類、野菜、キノコなどに多く含まれ、便のカサを増やす働きがあります。一方、水溶性食物繊維は海藻類、寒天、果物などに多く含まれ、便を柔らかくするほか、脂肪や糖分の吸収を緩やかにしたり、善玉菌のエサになったりします。
近年では、水溶性食物繊維に食欲を抑制する効果や内臓脂肪を減少させる効果、さらにはさまざまな不調や病気を予防する効果があることが明らかになっており、重要視されています。
その他に気をつけること
夕食は就寝3時間前までに
よく噛んで食べる
ストレス管理をする
適度な運動をする
十分な睡眠を取る
体をあたためる
体を温める食材を摂ったり、運動や入浴で温めることが腸の働きを活発にします。
抗生物質の乱用を避ける
食品添加物を避ける
アルコールや喫煙
サプリメントの活用
腸内フローラは、私たちが健康でいられるか、あるいは病気になるかを左右する、きわめて重要な要素となっています。腸内フローラを整えることこそが心と体の健康維持に直結していると考えられています。
腸は全身の臓器と連携して健康を守る存在
腸と脳との関係
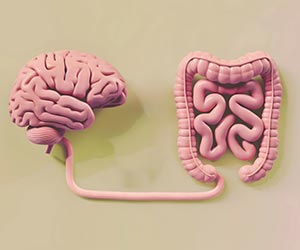
腸は、「腸管神経系」と呼ばれる1億個以上の神経細胞を持っており、脳からの指令なしに独自の判断を下せる自律神経系を備えています。
腸は消化、吸収、排泄など、生物が生きていくために最も重要な働きを担っているため、体にとって有害なものが侵入したときに、脳からの指示を待たずに独自に判断して動きや反応をコントロールするシステムを持っています。
また、脳と腸は互いに密接に連携しており、この関係を「脳腸相関」といいます。たとえば、ストレスを感じるとおなかが痛くなり、便意を催すなど、脳が自律神経を介して腸に刺激を伝えたり、逆に、腸の状態が脳の健康や感情に影響を与えることも分かっています。
心を安定させ、幸せを感じやすくする神経伝達物質
腸は「セロトニン」などの神経伝達物質を作り出す働きもしています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、心を安定させて幸せを感じやすくする物質を作り出す働きを持っています。実際、体内のセロトニンの90%以上は腸で作られているため、腸内環境が乱れると、気分の落ち込みやストレスを感じやすくなるとされています。
また、GABA(ギャバ)という抗ストレス作用のある物質を生成する働きもあります。GABAにはセロトニンと同じように興奮を引き起こすホルモンを抑えて脳や脊髄の働きを穏やかにする作用がある他、高血圧の予防、睡眠障害の改善に役立つこともわかっています。
近年の研究でわかってきたこと
近年の研究で、腸と脳が「腸内細菌」を通じて深く結びついていることがわかってきました。私たちの腸には多くの細菌が住んでいて、この細菌たちが作る物質が、腸を通じて脳にも影響を与えることがあるのです。
たとえば、腸内細菌のバランスが崩れると、うつ病などの心の不調を引き起こしやすくなることがわかっています。さらに、パーキンソン病やアルツハイマー病といった脳の病気も、腸内細菌の状態と関係があることが示されています。
また、脳だけでなく、心臓、肺、肝臓など他の臓器の働きにも影響を及ぼしていることも分かってきています。
つまり、腸は全身の臓器と連携しながら身体機能のバランスを整え、健康を保っているのです。
つまり、腸はただの消化器官にとどまらず、脳や全身の臓器と連携してメンタルや健康全般に影響を与える重要な役割を果たしています。腸内環境を整えることで、心身ともに健康な生活を送るための土台が作られるのです。
便でわかる腸の健康状態
腸内環境を整えることがいかに大切かというお話をしてきましたが、簡単に自分の腸内環境をチェックする方法があります。それはウンチです。
ウンチを見ればある程度腸の健康状態がわかります。
人が食べたものは内臓で消化吸収され、約24~72時間後に便として排泄されます。
健康な人の便は、80%が水分、残りの20%が食べ物のカス、剥がれた腸粘膜、腸内細菌とその死骸です。
便の状態は腸の健康状態を映し出す「バロメーター」とも言えるので、毎日チェックするようにしましょう。
理想的なウンチ
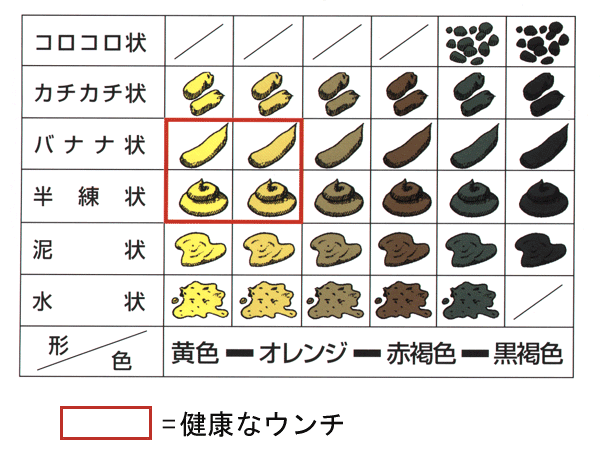
黄色から黄色がかった褐色が良い色です。
黒っぽい色であることは腸内フローラが乱れ、悪玉菌が増えているのかも知れません。
逆に白っぽい便は胆汁の分泌が減っている可能性があり、肝臓や胆管のトラブルが疑われます。
健康なウンチは刺激臭ではなく、発酵性のニオイになります。悪臭がする場合は悪玉菌が多いサインかもしれず注意が必要です。
ほどよい形状はバナナ状でスムーズに出るほどよい硬さの便です。
コロコロした硬い便は、水分不足や便秘の兆候で、腸内環境が乱れている可能性があります。反対に泥状や水っぽい便は腸が過敏になりすぎている状態で、こちらも腸内細菌のバランスが乱れている場合もあります。下痢よりも便秘に注意が必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください
大便で健康チェック! ウンチ確認表
大便を見れば自分の健康状態が一目瞭然!じゃあ、どんなウンチが健康的なの?色、におい、やわらかさ・・・。あらゆる面から自分の体調がわかる「健康測定」ウンチ君!



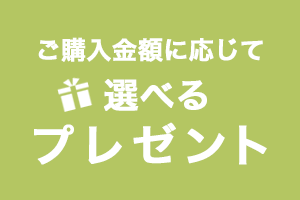
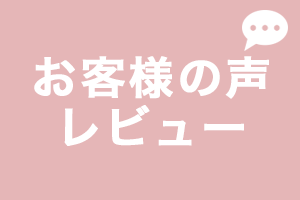
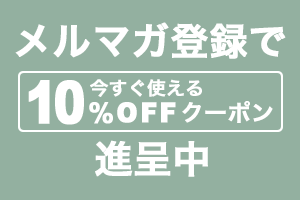
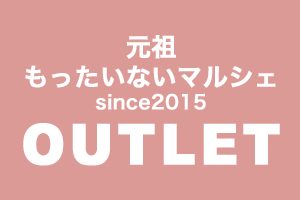
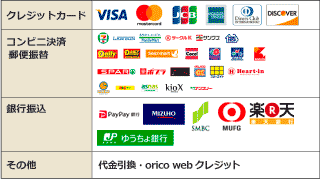











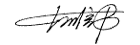










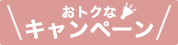




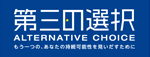




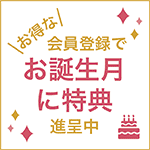
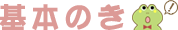
 がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)
がんはたくさん種類があって考え出すと怖くなりますが、予防のために日ごろ気をつけることはなんですか。(マラソンをがんばっている50代主婦)