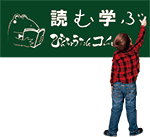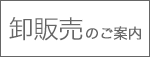お茶パワー『べにふうき』は
販売終了いたしました。
ご愛顧ありがとうございました。
幻のお茶とも言われている
現代人に最適なお茶を粉末にしました!
一部の愛飲者の方から「幻のお茶」ともいわれてきた「紅富貴」を
微粉末化したメチル化カテキンとストリクチニンが多く含まれているお茶です。
|
 |
 |
べにふうきとは? |
|
 |
幻のお茶「べにふうき」 |
- 紅茶系の茶葉「べにふうき」
-
「べにふうき」とはお茶の品種のひとつです。普段緑茶として飲んでいる茶葉は、「やぶきた」や「ゆたかみどり」という品種茶で、緑茶にするために改良された茶葉ですが、「べにふうき」はというと、紅茶品種なのです。
「べにふうき」茶は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構野菜茶業研究所(元農林水産省野菜・茶業試験場)にて育成され、1993年に命名、農林登録された品種です。
「べにふうき」茶は、1965年に、アッサム雑種の紅茶「べにほまれ」を母(種子親)に、香りの良いダージリン系「枕Cd86」を父(花粉親)に交配されました。
このように、もとは紅茶用として開発されたアッサム種に近い品種であったため、香りがふくよかで渋味が強いという特長を持っています。しかし、農林登録後、紅茶が輸入自由化になり、安くて美味しい海外の紅茶が輸入され、「べにふうき」の栽培も衰退していました。その結果、「べにふうき」は鹿児島県や静岡県でわずかに生産されるも普及には至らず、一部愛飲者の方々からは、「幻のお茶」ともいわれてきました。
しかし、「べにふうき」茶は、カテキン含量が多く、特に茶葉中に有用成分「メチル化カテキン」を豊富に含んでいることがわかり、今、新たに注目を集めています。
また、樹勢が強く多収で、病害にも強いことから、農薬を減らすことができ、安全性、安心性の高い農産物としての期待も高まっています。その後、気候等の栽培条件が「べにふうき」に適しているという理由で、鹿児島県が現在、中心的な生産地となっています。鹿児島県は、茶業が盛んで生産量も静岡に次いで全国第2 位を誇るお茶どころです。
この鹿児島県で、農家、県、県経済連、JAならびに、研究機関、メーカー等が参加する「べにふうき育成会」が2003 年に発足し、その後着々と本格的な生産体制が整いつつあります。
「べにふうき」緑茶関連年表
| 年号 |
トピックス |
| 1965年 |
農林省茶業試験場(枕崎)で「べにほまれ」を種子親、「枕Cd86」を花粉親とした交配が行われる |
| 1966~1992年 |
上記交配実生中より枕崎3 号(後の「べにふうき」)を選抜 |
| 1993年 |
「べにふうき」を紅茶用・半発酵茶用品種(茶農林44 号)として農林登録 |
| 1996年~2001年 |
農林水産省野菜・茶業試験場(現・野菜茶業研究所)、九州大、静岡県立大、静岡大が、生研機構基礎研究推進事業として、「茶機能検定系の構築と茶成分新機能の解析」を共同で推進 |
| 1999年 |
野菜茶業研究所が静岡県立大、九州大とともに新たな茶葉中成分「メチル化カテキン」を見出し、論文を発表。「メチル化カテキン」を多く含む「べにふうき」に注目が集まる |
| 2001年~2006年 |
「茶コンソーシアム」が発足、「茶の作用を利用した食品の開発」プロジェクトがスタート |
| 2003年 |
鹿児島県内の農家、県、県経済連、JAならびに、研究機関、メーカー等が一体となり、「べにふうき育成会」が発足 |
- メチル化カテキン
-
緑茶に含まれる「カテキン」という成分があることはご存じだと思います。
いまや緑茶飲料としてだけでなく、緑茶成分入りとして洗剤や石鹸、消臭剤やガムなどいろんな商品に含まれています。
そのカテキン類の中でも、「メチル化カテキン」という成分が、農業技術研究機構野菜茶業研究所の研究で、すばらしい作用があることが分かったのです。そして「メチル化カテキン」を一番多く含む品種が「べにふうき」だったのです。
「べにふうき」は紅茶品種ですが、メチル化カテキンは発酵すると消滅してしまうため、緑茶に仕上げることになりましたが、どうしても渋みの強いお茶になります。しかしパウダーにすることで渋みを和らげ、さらにそのまま全部飲んでいただける形態にしました。
|








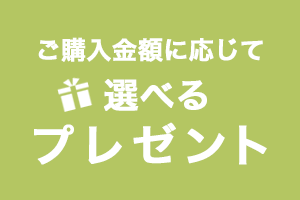
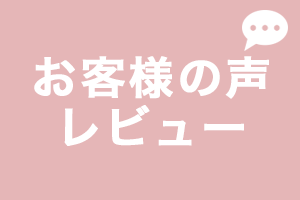
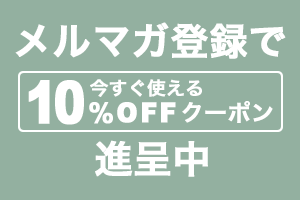
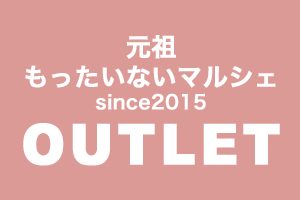
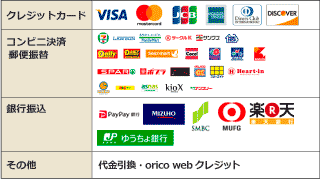











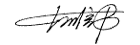










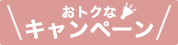




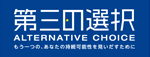




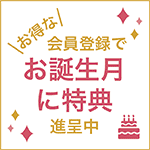
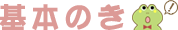
 痩せたくて入会したジムでプロテインを勧められました。普段から豆腐や肉を食べていますし、マッチョになりたいわけではないのですが、摂る必要はあるでしょうか?(推し活に夢中の母)
痩せたくて入会したジムでプロテインを勧められました。普段から豆腐や肉を食べていますし、マッチョになりたいわけではないのですが、摂る必要はあるでしょうか?(推し活に夢中の母)